
こんにちは。書評ブログ「淡青色のゴールド」へようこそ。本記事は『ハッピークラシー――「幸せ」願望に支配される日常』の書評記事です。ウェルビーイングや幸福度など個々人の幸福が社会的な目標としても語られることが増えてきている中で、改めてその背景や文脈を捉え直す必要性を訴える書籍です。
- 内容紹介
- 『ハッピークラシー』は何を語る本か(簡単な要約)
- 「幸せの科学」の根拠が不確かなことがなぜ注目されていないのか
- 不平等であるほど幸福度が増す?
- ポジティブ心理学と自己責任論の共犯関係
- 社会の理想としてウェルビーイングを目指すことの意義
- 幸せの科学を疑うことは幸せを目指すことを否定することではない
- 『ハッピークラシー』を読んだ人にオススメの本
内容紹介
本書のタイトルの「ハッピークラシー」とは「幸せHappy」による「支配-cracy」を意味する造語です。コーチングや自己啓発など個人として幸せを追求することの価値や「自分らしく」生きることの価値が強く求められ、さらには幸福度やウェルビーイングなどのキーワードから国の政策としても幸せであることが追求されるようになってきています。「幸せ」「幸福」はそれ自体がポジティブな意味合いを持つものであり、反対する人が居なさそうですし、その必要性も感じにくいものではありますが、実はこうした文脈の根拠となっているポジティブ心理学の科学的根拠は完全に確立されている訳ではなく、批判的に捉え直すことが必要だと言います。また、誰しもが捉え方次第で幸福になれるという発想は、新自由主義の自己責任論を加速する考え方になってしまう部分もあり注意が必要だといいます。本書は心理学者エドガー・カバナスと、社会学者エヴァ・イルーズによる共著で、心理学・社会学の両面から幸せの科学やポジティブ心理学の背景や社会的な影響について捉え直す視点で書かれています。
Amazonの内容紹介から引用します。
「現代の資本主義が抱える幸せへの強迫観念。善意によって築かれた理想像を企業と政府が蝕むにまかせる怪しげな科学。これらに対する洞察力あふれた批判」『ニューサイエンティスト』誌
「幸せの産業は、よい人生についての私たちの考えをどう変えてきたのだろう? そしてその代償はなんだったのだろう? エドガー・カバナスとエヴァ・イルーズはその批判的研究によって、蔓延する新自由主義の論理と、幸せをめぐる現代政治がもたらす有害な帰結を効果的に論証している」ディディエ・ファサン(プリンストン大学 社会学教授)
「本書は新自由主義社会において人びとが幸せ探しの下僕と化している状況を明察している」『サイコロジスト・マガジン』
「それは涵養され、理論化され、ビジネスの道具となり、書籍となり、セミナーとなり……さらには生産性の原動力にさえなった。社会でも職場でも、幸せは至上命令となった」『ルモンド』紙
「鮮やかな調査研究と見事な議論によって、本書は現代社会における幸せへの執着を痛烈に批判している。エドガー・カバナスとエヴァ・イルーズは幸せの科学の欠陥、無定見、短絡を追及し、それが経済格差の原因は個人の心理レベルにあり社会構造の問題ではないという論調の骨格となってきたことを示した。新自由主義がいかにして心理学の流儀への傾斜を強め、それによって「自信」「レジリエンス」「ポジティブな感情」を善として喧伝してきたかを理解するための必読書」ロザリンド・ギル(ロンドン大学シティ校 文化社会分析学教授)
「幸せの追求はじつのところ、アメリカ文化のもっとも特徴的な輸出品かつ重要な政治的地平であり、自己啓発本の著者、コーチ、[…]心理学者をはじめとするさまざまな非政治的な関係者らの力によって広められ、推進されてきた。だが幸せの追求がアメリカの政治的地平にとどまらず、経験科学とともに(それを共犯者として)機能するグローバル産業へと成長したのは最近のことだ」(「序」より)。
ここで言及される経験科学とは、90年代末に創設されたポジティブ心理学である。「幸せの科学」を謳うこの心理学については、過去にも批判的指摘が数多くなされてきた。本書はそれらをふまえつつ、心理学者と社会学者の共著によって問題を多元的にとらえた先駆的研究である。
「ハッピークラシー」は「幸せHappy」による「支配-cracy」を意味する造語。誰もが「幸せ」をめざすべき、「幸せ」なことが大事――社会に溢れるこうしたメッセージは、人びとを際限のない自己啓発、自分らしさ探し、自己管理に向かわせ、問題の解決をつねに自己の内面に求めさせる。それは社会構造的な問題から目を逸らさせる装置としても働き、怒りなどの感情はネガティブ=悪と退けられ、ポジティブであることが善とされる。新自由主義経済と自己責任社会に好都合なこの「幸せ」の興隆は、いかにして作られてきたのか。フランス発ベストセラー待望の翻訳。
本書の構成
本書は以下のように構成されています。
序
第1章 あなたのウェルビーイングの専門家
第2章 よみがえる個人主義
第3章 仕事でポジティブであること
第4章 商品棚に並ぶ幸せなわたし
第5章 幸せはニューノーマル
結論
解説 山田陽子
原注
索引
本書をオススメする人
本書は以下のような方に特にオススメです。
- 「ウェルビーイング指標」「幸福度」など社会指標や政策導入に関心のある方
- コーチング、カウンセリング、自己啓発など個々人の幸福追求を促進することに関心のある方
- 社会的弱者の支援などに関わっている方
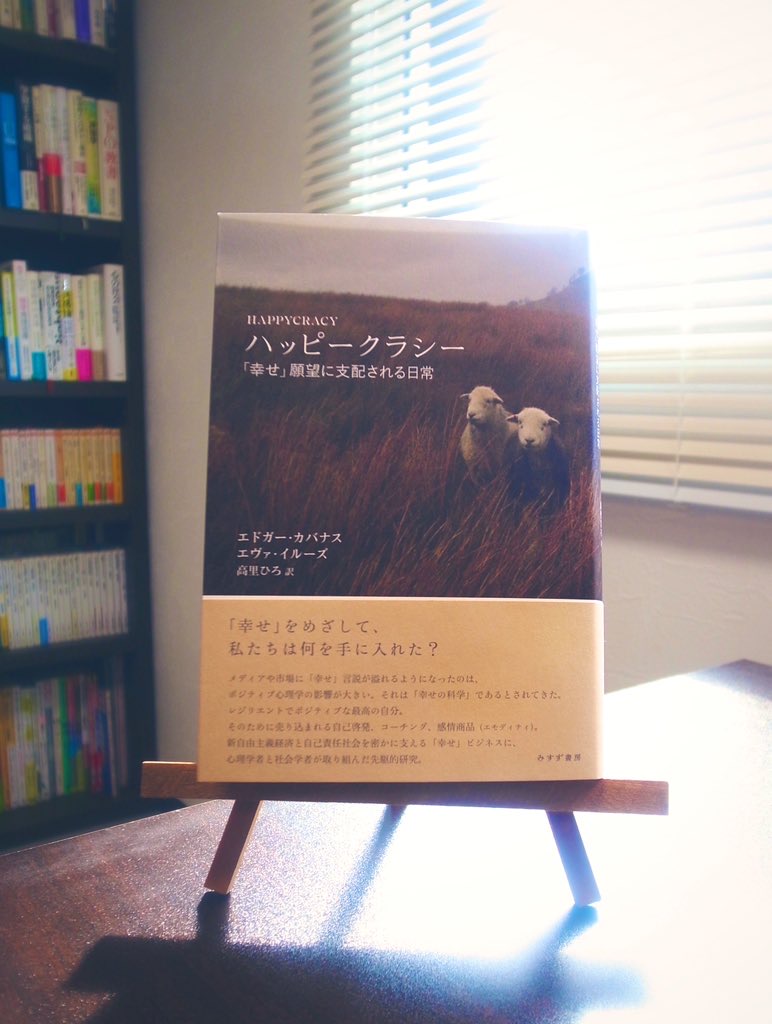
『ハッピークラシー』は何を語る本か(簡単な要約)
本書は「幸せ」という考えを批判的に捉え直す本なのですが、なぜ著者たちはそのような本を書いたのでしょうか。それは決して「幸せ」を否定するためではありません。
序章から少し引用してみましょう。
本書は幸せに反対するわけではないが、幸せの科学が説き広める「いい人生」という還元主義的な考えには反対する。人々をいい気分にさせるのは立派な心づもりだ。それは言うまでもない。しかしこの点にかんして幸せの科学が提供するものを検討すると、その幸せという考えには、深刻な限界、物議をかもす主張、矛盾する結果と悪影響がないとは言えない。
著者たちは「幸せ」を否定はしないが、幸せの科学が推し進める動きはそのまま受け取ることはできず、立ち止まって考えるべき懸念が多くあると言います。具体的には認識論的、社会学的、現象学的、道徳的という4つの側面からそれぞれ重大な懸念があると言います。著者たちの疑問と現時点での答えはそれぞれ以下のようなものです。
認識論的懸念…幸せの科学は本当に科学的かつ客観的なのか?→幸せの科学はいくつかの根拠のない前提、理論的な矛盾、方法論上の不足、証明されていない結果、民族中心的で必要以上の一般化に依存しており、この科学の主張を客観的な事実として無批判に受け入れるのは難しい。
社会学的懸念…幸せの概念は誰の利益やイデオロギーの前提に役立っているのか?その社会的推進の拡大はどのような経済的また政治的影響をもたらすのか?→幸せの科学とその周辺に拡大した幸せ産業は自己責任論の正当化に大きく貢献している。さらに社会的な構造の問題ではなく、あるのは個人の精神的な力不足だとする考えを強化し新自由主義派の推進する個人主義社会に利するものである。
現象学的懸念…幸せの科学はセラピー的なナラティブに依拠しているが、それは「何かもの足りない」「自分らしくなれない」「自己実現できない」といった苦しさを扱い、それを解消すると謳っている。そのようなナラティブにおいて、幸せが、結末のはっきりしない動くゴールであるにも関わらず必要不可欠なものとして確立されたことで、新しい種類の「幸せ探しびと」が生み出された。彼らは内なる自分にひたすら固執し、自分の精神的欠点を直すことに次々と夢中になり、自己変革と改善について果てしなく心配し続ける。これは幸せ産業の格好の顧客を生み出すことである。
道徳的懸念…幸せであることやポジティブであることを、生産性、機能性、善良さ、正常さと同一視し、不幸せをその正反対とすることで、幸せの科学は私たちを、苦しみと幸せ二者択一の重大な岐路に立たせる。人生において不運は避けられないはずだ。しかし、幸せの科学は苦しむか幸せになるかは個人的な選択だと主張し、逆境を個人的成長の機会として利用しない人間は、その個人の事情に関係なく、不運を望んでいるのではないか、自業自得ではないかと思われる。幸せの科学は幸せになることを強いるだけでなく、もっと幸せで成功した人生を送らないのをわれわれの責任にする。
本書では幸せの科学が市民権を得てきた歴史や背景も含めて整理した上で、これら4つの懸念についてさまざまな調査研究等を引用しながら解説していきます。
第1章では、幸せの科学と政治の関係に焦点があてられます。幸せの科学の中でも最も影響力の大きい分野であるポジティブ心理学と幸せの経済学はどのように始まり、広がっていったのか。両者の基本的な主張や狙い、方法論としての前提、学会組成や社会への広がりなどから幸せ研究が政府の中に入り込んでいったことについて解説されます。特に幸せを客観的で計測可能な変数として提示する手法をとったことが、政治的決定の方向性を決める主要で正統な基準となり、社会的な進歩度合いの評価や、不平等などの道徳的あるいはイデオロギー的な課題を道徳とは無関係に技術的に解決できると主張している点などが論じられます。
第2章では、幸せと新自由主義の関係がとりあげられます。ポジティブ心理学の中立的で権威ありげな言説が個人主義を正当化するのに役立っていたことを指摘します。その上で、ポジティブ心理学が先行き不透明な時代に答えを求める人々の拠り所となりつつある一方で、幸せの科学の提供する処方箋は幸せへの終わりない渇望を生み出している状況を明らかにし、そうした論理を教育に導入することを批判しています。
第3章では、幸せの科学と企業等の組織の関係が論じられます。労働者にとって自分の幸せに投資をすることが必要条件となっていることを指摘し、企業も社員の管理やニーズに応えることに幸せの科学を利用するようになっていること、企業文化に対する服従を促す方向につながっていること、さらには不景気等の市場の不確実性、就職難や職務競争等の負担をすべて労働者個人に背負わせる論理になっていることが指摘されます。
第4章では、セラピー、自己啓発本、コーチング、カウンセリング、自己啓発アプリなどの幸せを扱う「感情商品」やサービスについて論じられます。感情を自己管理することや自分らしくあること、それらにより成功した人生を送り続けるために、個人は自らをプロデュースしなければならず、感情商品産業の市場がより大きくなっていきます。
第5章では、幸せの科学者たちが論じるポジティブな感情とネガティブな感情の明確な区分の妥当性について分析し、その区別にはいくつかの落とし穴があることを指摘します。さらに、幸せと苦しみの関係について論じ、苦しみを副次的で避けようと思えば避けられる、究極には無益なものとして捉えることの危険性について思索的に検討がなされています。
「幸せの科学」の根拠が不確かなことがなぜ注目されていないのか
本書が指摘する懸念、疑問はどれも重大なものですが、特に論点となるのは著者たちが「認識論的懸念」といっている「幸せの科学の根拠は確かで客観的なものなのか」というものでしょう。この点について著者たちの指摘は当然「否」であり、その根拠は本書の中でいくつも提示されていきます。その指摘は至極真っ当なものだと思いますが、個人的にそれ以上に興味を惹かれたのは、なぜそのような根拠の不確かなものが、客観的で科学的なものとしてこれだけ社会的な影響力を持ち、特に政治にも導入される大きな流れを作っていくことができたのか、という点です。
この点についてはそれこそ客観的で科学的、論理的な要因が明確にあるわけではなく、それこそ政治的なものも含めた人間関係や経済的社会的な関係の中で影響が形作られていったのだと思います。例えば、ポジティブ心理学が登場した当初の経緯として以下のような解説がなされます。
じつのところポジティブ心理学は、「専門家」と非専門家との間に明白な境界線を引くために実証科学の語彙を用いて、非専門家に敵対的な姿勢をつねに見せていた。たとえばセリグマン(ポジティブ心理学の創設者)も、「ポップ心理学や自己啓発本とは違い、わたしの書いたものが信用されるのは、その根底に科学があるからだ」と主張したが、その区別はほとんどの場合、願望のまま終わった。
この辺りは非常に興味深いところです。
ポジティブ心理学はその登場時点からそもそもの特徴として「実証科学的」であることを標榜しており、他の非専門的非科学的な取り組みとはその点において異なるものであることを主張していた。そのことによって注目を集めていたが、そもそもその根拠が確かには示されていなかったといいます。この状態のままでは現在ほどの大きな影響力は持ち得なかったと思うのですが、ここに市場という力学が関わってきているというのが著者たちの指摘です。コーチングというすでに大きな市場を持っていた分野に対してはポジティブ心理学側から論文を発表して近づくということが行われたことや、つねに新たな研究分野を開拓することで研究資金を呼び込むことが求められる学問分野の経済的事情と協働関係を作ったこと、さらには当初は非科学的として敵視していたはずの自己啓発ワーカーたちとも相互依存的な関係を築いていったことが指摘されます。ポジティブ心理学には発足当初から多くの批判が寄せられてきたが、こうした市場との良好な関係の中で成長をし続けたといいます。
科学至上主義というか科学が宗教的に信奉される社会においては事実として科学的であることよりも「科学的であると信じられること」がより重要であるという社会構築主義的な興味深さと怖さを感じます。「事実として科学的であること」はこれだけ複雑化、専門化が進んだ社会において一個人があらゆる問題について確かめながら生活をするというのは望んだとしても現実的ではなく、そもそもそうしたことを願望として持つことすら容易ではないので、この問題はポジティブ心理学に限らずあらゆる分野について言えてしまいます。どうしたら良いのかさっぱりわからなくなりますね。
幸せの科学はいまや学会と市場の協働を超えて政治分野にも大きな影響力を持ってきています。国民総生産(GNP)に代わる指標として国民総幸福量(GHP)等の指標が導入されるようになってきていますが、個々人の幸福が同一尺度として計測可能であるのかや幸福が目指すべき自明の目標であるのかといった問いは棚上げにされたままですし、ポジティブ心理学者たちはそもそもこの問いに対して回答が不要だと主張しています。
幸福は究極の目標だ。なぜならほかの目標とは異なり、幸福は自明の善なのだから。
これに対して著者は次のように指摘します。
ここで注意すべきなのは、この主張は証明されたものではなく仮定であり、科学的ではなくイデオロギー的であり、レイヤード自信が言うように、正しさを証明するそれ以上の外的な理由をもたないトートロジーだということだ。
皆さんはどのように考えるでしょうか。
不平等であるほど幸福度が増す?
国民幸福度や経済福祉指標、人間開発指数等の指標が導入されるようになってきたことはNPOやNGO等で社会的弱者の人道支援に関わる人やそうした取り組みへの関心を持つ人、あるいは社会的な公正や平等を重視するリベラルな価値観を持つ人にとって「良い動き」として捉えられることが多いように思います。非営利組織の支援を主な仕事としている私自身もそうです。そしてアドラーやセリグマンらのポジティブ心理学者の提唱者たちは、こうした指標を公共政策に活用することは民主主義的で公平なものであると主張しています。
しかし、著者たちはむしろ逆の効果が生まれているといいます。所得格差と資本の集中は幸福とや経済発展と正の相関があると大規模なデータベースに基づく調査で証明されてきており、特にそれは開発途上国において顕著である、と。社会の不平等度合いが増し格差が大きくなればなるほど、個人は将来の自分の機会が増大するという希望を持つようになるという効果があるということは、つまり社会全体の幸福度を高めるためには不平等や格差を大きくすればするほど良いという結論になってしまうということです。それがわたしたちの目指す幸福な社会でしょうか?そうではないはずですよね。
一方で上記のような結果は発展途上国における結果であり、先進国ではまた違った結果が出ています。先進国においては不平等は個人の幸せに「関係ない」、つまり「マイナスにもプラスにもならない」という結果になるようです。これでは幸福度指標を採用している国において、政策決定者たちによって不平等を縮小するような政策的合意がなされる訳はありません。
さて、わたしたちが目指すべきなのか個人の「幸せ」でしょうか。不平等の解消でしょうか。平等であることと幸せであることは直感的には結びつきやすい価値観で生きるわたしたちですが、今採用されている指標が指しているものが何なのかを含めてしっかりと立ち止まって考える必要がありそうです。
ポジティブ心理学と自己責任論の共犯関係
わたしたちが目指すべきなのは不平等の解消なのか幸せなのか、という書き方をしましたが、そもそも幸福というのは文化的、道徳的、人類学的さまざまな観点からいって中立的な概念ではありません。にも関わらず、正義や、思慮分別、団結など他の様々な価値観ではなく幸せが先進資本主義社会で大きな影響力を持つようになったのかというと、幸せの重視が個人主義を活性化する働きを持っており、新自由主義社会と相性が良かったからだと言います。
ポジティブ心理学の提唱者セリグマンは「幸福の方程式」を作り出しました。
H(永続する幸福のレベル)=S(その人にあらかじめ設定されている幸せの範囲)+V(自発的にコントロールする要因)+C(生活環境)
この方程式によってセリグマンが主張するのは、収入や教育社会的地位などの生活環境が幸せに関わる程度は低く、幸せの90%は個人的あるいは心理的な要素に起因していること、そして、個人の選択・意思の力・自己鍛錬などによって手に入れることが可能なことです。生活環境については重要なのは環境そのものではなく、環境に対する個人的・主観的認知であるというのがセリグマンの主張です。これらは科学的に明確な根拠を持っているわけではありませんが、ポジティブ心理学だけではなく、コーチングやカウンセリング等でも基本的にはこの「個人の捉え方」に帰結させていく力は存在しています。こうしたすべてを個人の捉え方、あるいは努力に還元してしまう論理は、「幸せでないのは、成功していないのは努力をしていないからだ」という自己責任論に簡単に通じてしまいますし、社会の現状の様々な課題(経済的社会的なさまざまな格差や差別)を見て見ぬ振りをする現状追認的な政治と非常に相性が良いものになります。
こうした「幸せは個人の捉え方次第」という発想の問題点は政治レベルでいえば社会的マイノリティに対する差別や格差に対する無理解を容認したり促進したりすることにもつながってしまいますし、主に第3章で述べられる通り企業のマネジメントにも取り入れられることで例えば不況などの経済全体の問題や企業の戦略判断のミス等の影響を個人が被った場合にも、その窮地への対処や回復はすべて個人の責任に帰せられてしまうという形で社会の構成員の多くにとって無関係な問題ではありません。
特に昨今ではコーチングやカウンセリングの活用が個人でも組織でも大きく広がっていたり、マインドフルネスなどへの注目も集まっています。個人的にはこれらの手法に対しての関心や理解も十分以上に持っており、個別の手法が持つ効果や成果をすべて否定する気もありません。ただし、基本的にこうした手法を能動的に活用できる発想を持っていたり、活用できる社会的な状況・立場にある人は、基本的には資本主義社会における勝ち組のエリート層であることがほとんどであるということはしっかりと理解しておくことが重要でしょう。この点を忘れてしまうと簡単に暴力的な自己責任論と通じてしまいます。
特に、社会的な弱者を支援するような活動に携わる場合にこの「すべては個人の捉え方次第」という発想は十分な注意が必要だと感じます。例えば子どもの貧困に関わる活動として子ども支援を行っているとして、活動の成果を受益者の変化によって定義したり時には計測したりといったことが求められるようになってきています。こうした文脈では受益者である子どもの内面の変化を捉えようとすることや、あるいは介入の手法としてコーチング的な手法が用いられる場合もありますが、例えばその成果を、子どもの主観的な幸福度だけで捉え、客観的な社会的状況や地位などの生活環境を無視してしまってはならないでしょう。また、例えば「子どもが自分の人生を自分で切り開いていく力を身につける」といった形で子ども本人の認知に還元してしまうような捉え方も、対象とする受益者の状況等によっては危険なことになってしまう可能性があります。この辺りは私自身がこうした社会的成果の定義や考え方を研修やコンサルティングで伝える立場になることも多いので、しっかりと考えていきたい点です。
社会の理想としてウェルビーイングを目指すことの意義
近年ウェルビーイングという言葉が一般的な言葉となってきました。私が普段仕事を一緒にしている非営利組織業界においても、ビジョンや中期事業計画の中に目指すべき社会・地域像として「ウェルビーイング」という言葉が入ったり、あるいはそれらを計測・把握する指標として幸福度指標が参照されるといったことが増えてきました。
幸福という価値観自体をどのように捉えるのかという点自体もしっかりと考えていきたいと思いますが、NPOや市民活動の文脈ではポジティブであることとは逆に、ネガティブであることが社会変革の源泉となってきたということも忘れてはいけないことでしょう。
社会学の社会構築主義の立場では、社会課題というのは何か特定の害悪となる状態のことではなく「これは解決されるべき課題である」という認識が社会的に広がることによって初めて社会課題として存在することができると考えます。この考え方においては、格差があること、差別があることなどをその当事者やその支援者が社会に対して訴える(クレームを申し立てる)ことが社会課題化されること、そしてそれが解決に向かっていくためのスタートだと言います。実際に人種差別、女性差別、障害者差別などの様々な問題はそのようにネガティブな状態を認識し、個々人の努力や捉え方のレベルではなく社会的なレベルにおいて解決されるべきであるという動きを作ることで社会制度や社会の認識に変化を起こしてきました。
特に社会的な弱者やマイノリティの支援を行っているような活動の場合、こうした文脈の重要性は忘れてはならないでしょう。最終的な社会の姿として個々人の幸福を理想とすること自体が悪いことはないと思います、というかそれに反対することは簡単ではありません(それこそ幸福という価値観そのものを批判的に捉え直す作業からやる必要があります)が、ウェルビーイングや幸福度などの個人主義的な思想が大きな役割を果たしたときに、そこに至るための手法や活動・事業の形やその成果も個人(の内面の変化)にばかり還元されてしまい、社会全体の構造を見る視点が抜け落ちてしまうことが無いように注意する必要があるのではないでしょうか。
幸せの科学を疑うことは幸せを目指すことを否定することではない
非常に考えがいのある本で、まだまだ考えたいこと、問いかけたいことがたくさんあるのですが、だいぶ長くなってしまったのでこの辺りにしておきます。(個人の発想や認知の重要性という文脈では、当事者研究やナラティブ・アプローチなどの社会構成主義的な文脈との関係をどのように考えるべきかといった点も深堀りしたいのですが、これだけでだいぶ話が長くなりそうなので、別の機会にします)
最後になりましたが、基本的に個人が幸せになることや目指すこと自体を否定するつもりはありませんし、私個人としても幸せになりたいと思っています。が、ポジティブ心理学を始めとした幸せの科学やその周辺の幸せ産業、そしてそれらの政治的な影響といった点には十分に注意し、批判的な議論を行いながら向き合っていくことが必要かと思います。
『ハッピークラシー』を読んだ人にオススメの本
最後に本書を読んだ方や興味を持った方にオススメの本をご紹介します。
『心を測る』(デニー・ボースブーム)
幸せの科学に対する懸念や疑問の大きなものとして、そもそも幸福をどのように測るのか、測れるのかが明確になっていないというものがあります。本書は心理学、教育学、医学、統計学など様々な分野で活用される心理測定について、その背景にある考え方やモデル化の方法論まで、現在その手法がどのような考えに基づいているのかを詳しく知ることができます。
『感動のメカニズム』(前野隆司)
『ハッピークラシ―』は幸せの科学を批判的に捉える書籍でしたが、もちろん幸せの科学のすべてが無根拠だったり非科学的なものであるわけではありません。では肝心の幸せの科学はどのように科学的足ろうとしているのか。本書は日本の幸福論の第一人者である前野氏の研究内容を新書で簡単に知ることができるもので、「感動」という感情をどのように尺度化し、計測しようとしているのかや、それらの分析視点を活用してどのような研究を行っているのか事例紹介も含めて解説されています。
『ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術』(ラファエル A. カルヴォ & ドリアン・ピーターズ、渡邊淳司 (監修)、ドミニク・チェン (監修))
副題に「情報技術」というキーワードが入っている通り、本書の主題はITを始めとした技術的なアプローチです。心理計測は単純なアンケートやインタビューだけでなく、IT技術が活用される場面が多いですし、むしろこちらの方が主流になっていくはずです。現状どのような研究や技術活用がなされているのか現在地点を知ることができます。
『人間科学におけるエヴィデンスとは何か』(小林隆児、西研、竹田青嗣、山竹伸二、鯨岡峻)
人間の内面の変化や認識をどのように「科学的に」捉えていくことができるのか。『ハッピークラシ―』では幸せの科学への批判材料としてその尺度や計測方法、あるいは論理が科学的態度を装いつつ、科学的でないことがありました。本書は単純に自然科学的な意味合いでエヴィデンスを用意するのではなく、人間に向き合う科学ならではの手法として現象学的な視点を取り入れることが有効ではないかという仮説の元に5人の論者がそれぞれの研究や実践の面から論じます。
書評も書いておりますのでよければお読みください。
最後までお読みいただきありがとうございました。




