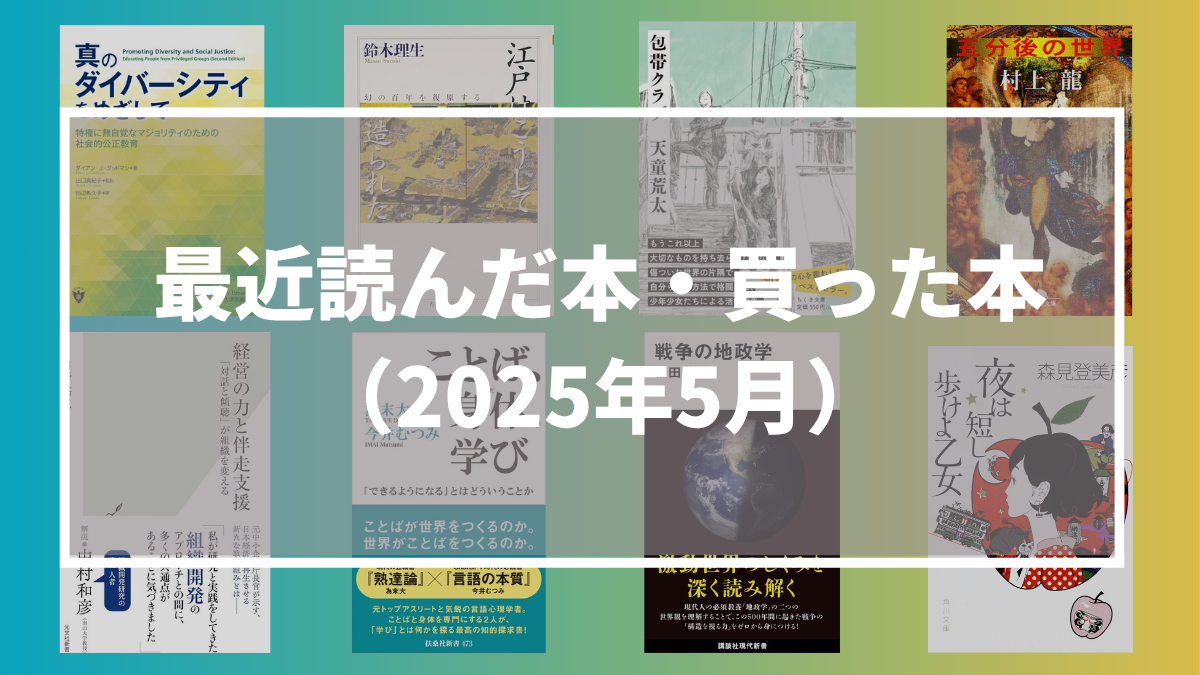
いろいろな本を読んで生きています。紙で読んだ本、電子書籍で読んだ本、オーディオブックで聞いた本と、あと買った本と。単に趣味の本もありますが、仕事に関係していたり考えたい問いがあって読む本もあるのでご紹介します。
読んだ本
紹介は読み終えた順です。
『真のダイバーシティをめざして 特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育』(ダイアン・J.グッドマン著)(田辺希久子、出口真紀子訳)
アメリカで社会的公正教育に携わる著者による力強い一冊。D&Iやあらゆる差別問題の啓発や教育等に関わる方、広くこどもの支援や教育に関わる方には一読をお勧めします。
中心となる考え方は社会的アイデンティティの発達段階をどのように理解し、変容を促していくことができるかということ。人にはそれぞれ複数の社会的アイデンティティがあり、優位集団に属するアイデンティティ(例:男性)と劣位集団に属するアイデンティティ(例:貧困家庭育ち)の両方がある。社会的アイデンティティの発達段階は一人の人間の中でもそれぞれのアイデンティティごとに異なるというのは確かにその通りで重要な指摘だと感じました。多くの場面でその点が見過ごされたり誤解されたまま話が進んでいて、それが事態をややこしくしたり、悲しい状況に陥らせたりしているのだろうなと。自分自身の傷ついたり、あるいは傷つけたりしてしまった場面をあれこれ考えることになったし、先月『アーレントと黒人問題』を読んでモヤモヤしていた「アーレントはなぜユダヤ人の立場で洞察できたことを黒人にはまったく適用できなかったのか」という点についても社会的アイデンティティの優位・劣位とそれぞれの発達段階がアーレントの中でもバラバラであったのだ、ということが同じくユダヤ人である著者のさまざまな整理や自身の経験の吐露からある程度腹落ちさせることができました。そして自分自身の中にもさまざまな社会的アイデンティティがあり、偏見や差別的な思考が頑なに残っている側面がいくつもあることも常に忘れずにいなくてはいけないことも強く感じましたし、その向き合い方のヒントもいくつももらえ、読んで良かったと感じる一冊でした。
『戦争の地政学』(篠田英朗)
ハウスホーファーを始めとする大陸系地政学とマッキンダーなどの英米系地政学。
大きく異なる二つの視点から歴史と現在の世界を概観する入門書です。単に表面的な学説が異なるということではなく、そもそもの国家観や人間観という根本から異なるというのはなるほど、と大きな気付きを得ました。具体例として、その見方の違いによってアメリカのモンロー主義の意味合いやWW1参戦の捉え方も全然違ったものになるというのはわかりやすかったです。
地理的制約が政治や国際関係に影響を与えるというシンプルで確からしそうなメッセージを持つのにどこか胡散臭いイメージが拭えなかった地政学について、その経緯と理由も概ね理解できた(特に地政学はそもそも学術的な学問分野ではないという点。私は政治学部出身ですが地政学の授業なんてなかったですしね)し、どの辺りは有用なのかという部分も理解できて良かったです。政治学者が概説する地政学ということで非常に納得感のある入門書だったのですが、こうなると無茶な論理を展開している本も少し読んでみたくなります。
『江戸はこうして造られた』(鈴木理生)
仕事も絡んだまちづくり・地域づくりへの関心と趣味としての歴史への関心が悪魔合体して読んだ本。
江戸という都市の成り立ちとその背景を経済的、機能的要因を柱に据えながら丹念に構成していく名著です。手にした動機がまちづくりという観点もあったので、江戸の都市計画的な部分に関心が強かったのですが、秀吉と家康がそれぞれ江戸をどのように捉えていたのであろうかという点について、江戸の経済的可能性に先見の明があったのは秀吉ではないか、そして鎌倉・室町時代からの江戸の位置付けと徳川が江戸を手にするまでの考察など「大江戸」成立以前のところもかなり興味深く面白かったです。
まちづくり・地域づくりなどの観点で仕事に役立つかというとなかなか難しいですが、趣味的にはめちゃくちゃ面白かったので大満足。江戸やその周辺の地形的な広がりやそれぞれの成り立ちや歴史的文脈の解像度がかなり上がったので、今後いまの東京や首都圏を見る眼も変わるし、時代小説、特に江戸の市井物を読むのがより楽しくなりそうです。
『包帯クラブ』(天童荒太)
タイトルはずいぶん前から知っていたのですが手に取る機会のないまま来ていた作品。先月読んだ『傷を愛せるか』で触れられていて、興味を引かれて読んでみました。
人生の中で傷ついた経験をした場所に包帯を巻く活動をする「包帯クラブ」を結成した高校生たちの物語。もう20年近くも前の出版ですが、「傷」や「ケア」への関心が高まる中で改めて読まれるべき作品ですね。傷ついていたこと、そこに傷があることを認めてもらうこと受け止めてもらうこと、たったそれだけのことが持つ意味は時に意外な程大きい、というか人に寄り添うケアの本質はたったそれだけのことしかできないということへの認識が重要なのかもしれません。色々なことを考えさせながら、それでも作品としてはちくまプリマーの初期作品ということもあり重くなりすぎずにライトに読める良い作品でした。
高校生当時を振り返る報告書、という体で語りが始まり、章と章の間に大人になった現在の登場人物たちからの「アフター」が断片的に語られつつ、過去と未来の両方から結末に近づいていく構成、小説でも映画でもまぁまぁ良くありますが、良いよね。
『本なら売るほど 2』(児島青)
先月読んだ1巻が良かったので2巻も買いました。本にまつわる、本を読む人の話というのはやはり本好きにはたまらないものがありますよね。各話に具体的な作品が登場する形式は『ビブリア古書堂の事件手帖』とも通ずるものがあり、あちらも面白いですがライトではあってもミステリーでもありますし、こちらは漫画なので気軽さがあって良いです。
第8話で登場した『ガダラの豚』。そういえば何年もずっと読みたい本リストにいれたまままだ読んでなかったのを思い出しました。この記事でそのうち読んだ本として紹介できたらいいな。
『経営の力と伴走支援 「対話と傾聴」が組織を変える』(角野然生)
福島の復興における中小企業支援の過程で「伴走支援」の手法に辿り着いた著者が率いたチームがどのような考え方で伴走支援を進めていたか、そしてその後どのように他地域へ展開していったか、の話。予算も人材も潤沢な公的組織ならではの伴走支援スタイルという感じもしますが、その点も含めて小さい中間支援組織や個人が行う伴走支援との、あるいは伴走先が営利企業ではなく非営利組織である場合の伴走支援との、それぞれ共通点と違いを整理するためのヒントは得られたように思います。著者らの取組みや考え方がまとめられた「経営力再構築伴走支援ガイドライン」も読んでみたい。非営利組織の伴走支援を生業にしている人でも私のようにフリーランスで動いている人よりは、各種の中間支援組織の職員の方などが読んだ方が直接的な示唆が大きそうだなと思います。
『五分後の世界』(村上龍)
出張時に寄った神保町の古本屋でふと手にした本。高校生ぶりぐらいの村上龍です。
広大な地下世界を築き連合国相手にゲリラ戦を続ける日本のある「五分後の世界」に迷い込む男の話。話の筋や世界観は現代においては珍しくはやり方になってしまっているものかもしれないが出版当時はどうだったのでしょう、と気になりますが、本作の本質は筋や世界観ではありません。戦闘描写やライブシーンの描写がとにかく圧倒的な密度と物量で、ぶん殴られたような衝撃を受けます。凄みのある文章といいますか。近現代史や現代へのメッセージなども色々含まれている作品だとも思いますが、文章表現そのもので迫るように語ってくる感じのする作品はまさに文学という感じがして良いですね。村上龍は未読作品ばかりなんですよね、もう少し読んでみようかな。
『ことば、身体、学び』(為末大、今井むつみ)
先月まで勅使川原真衣さんの著作で行き過ぎた「能力主義」のデメリットや課題についてあれこれ考えていましたが、一方で何かが「できるようになる」ことや「うまくなる」こと「成長する」ことなど、そうしたことの喜びや嬉しさというのは確かにあるわけですし、非営利組織の活動においてはそうしたものを「アウトカム」として目指しながら活動する場面も多くあります。勅使川原さんの著作では「機能」と説明されていたそのような側面についても改めて考えてみたくて読んでみたい本リストから選んだ本です。
内容は「できるようになる」ということについて言葉・言語の専門家である今井むつみさんと、アスリートという身体の学びの専門家である為末さんの対談書です。身体の学びには言葉が、言葉をはじめ学問的な学びには身体がそれぞれどのように関わっているのか、お互いの専門領域や経験を踏まえた解説、比喩、そして問いかけが絶妙なバランスで知的刺激が大変心地良い対談でした。為末さんの『熟達論』も続けて読むつもりですが、私が考えたいのは「コンサルティングなどの組織支援、組織開発等を適切にできるようになる・育成する」であり(アスリート的な文脈とは異なる仕方ではありますが)身体もことばも両方使う職種なので、本書のことばと身体の横断的な視点が重要なのかなと感じながら読みました。『熟達論』が終わったらもう一度戻ってきたいです。
『Mad Hope』(星野源)
星野源6thアルバム初回限定盤「Box Set “Poetry”」の写真詩集。星野源の詩は、良い。「伝えたいこともメッセージもない」と最近の星野源は言うのですが、暗さや辛さや憂いや虚無がちゃんとそこにあって、そのことが届く人、感じる人には救いであったり安心であったりします。歌とメロディがあってポップに昇華されている普段の曲、音楽という形ももちろん最高に良いのですが、それらが削ぎ落とされた言葉で味わうとまた違う感覚になってとても良いですし、そして写真や紙の手触り感があいまって一つの作品として味わいがすごかったです。満足。初回限定特典なのでご感心ある方はお急ぎを。
ここからは詩集という本の紹介の範疇からは少し外れますが、CDアルバムを購入するという体験について。今回のアルバム購入は私にとってかなり久しぶりの物理的なCD購入でした。Spotify等の配信で音楽を聴くことが当たり前になって何年も経ったことや、歳もとってきて10代の頃のように音楽に感動したりアルバムを楽しみにしたりすることもなくなっていくのだろうなとなんとなく思っていたのですが、今回はアルバムの発表からずっと楽しみにしていました。詩集やBlu-rayなどの特典があることで2枚(2Version)も購入することになったということで推し活的な側面も強かったのですが、物理的なCDを手にすることと一曲目からじっくりと曲を楽しむことというアルバムを味わう、という体験の楽しさをひさしぶりに楽しむことができました。アルバムツアーという訳ではないですが、アルバムの曲もたっぷり聴くことのできるツアーにも参加できまして、非常に楽しかったです。
『夜は短し歩けよ乙女』(森見登美彦)
たまに妙に読みたくなる森見節。京都の大学生活を舞台にしているということで『四畳半神話大系』と通ずる作品ですが、いやぁ本当にこの森見節で描かれる大学生活を接種するのがとうに大学を卒業したあとで良かったなとつくづく思います。こんなものを中高生あたりで読んでいたら大学生活への憧れが変な方向に捻れてどうにかなってしまっていた気がしますので。それぐらいハマる人には中毒性のある文章と世界観です。個人的には先に出会った『四畳半〜』の方が並行世界的な不思議感覚も含めて好みだけど、より人におすすめしやすい場面は『夜は短し〜』の方が多そうかなと感じています。
買った本
『わたしたちが光の速さで進めないなら』(キム・チョヨプ著)(カン・バンファ、ユン・ジヨン訳)
タイトルが印象的で気になっていた韓国の若手作家のSF短編集。最近の関心テーマとも重なるかなと思い購入。
『傷のあわい』(宮地尚子)
先月読んだ『傷を愛せるか』が良かったので続けて購入。執筆順としてはこちらの方が先で、『傷を愛せるか』がエッセイだったのに対してこちらは著者の本業により近いエスノメソドロジー的作品のよう。
『利他・ケア・傷の倫理学』(近内悠太)
近内さんの本は以前から気になっていつつもなんとなく手が伸びていなかったのですが、最近集中して読んでいるテーマをこれだけタイトルにつけられているのでさすがに読まないわけにはいかないか、、ということで購入。とても楽しみではあります。
『ケアと編集』(白石正明)
医学書院の大人気企画「シリーズ ケアをひらく」の編集者である白石さんの著作。大好きなシリーズでもあるので楽しみです。
『妊娠カレンダー』(小川洋子)
ひさしぶりに小川洋子さんの作品を読みたいなと思って本屋で眺めていたら、そういえば何作も読んできたけど芥川賞受賞作のこの作品を未読だったなと思い購入。
『公務員のためのマーケティング講座』(長浜洋二)
我がボスの新著。読まないわけにはいきません。
以上です。
「私もこの本読んだ!」というものがあれば感想を教えてくださると嬉しいですし、おすすめの本などもありましたらぜひぜひ教えて下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。






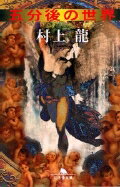

![Gen [Gen Box Set “Poetry”] [BOX + CD + BOOK] Gen [Gen Box Set “Poetry”] [BOX + CD + BOOK]](https://m.media-amazon.com/images/I/31Z+Tro50AL._SL500_.jpg)






