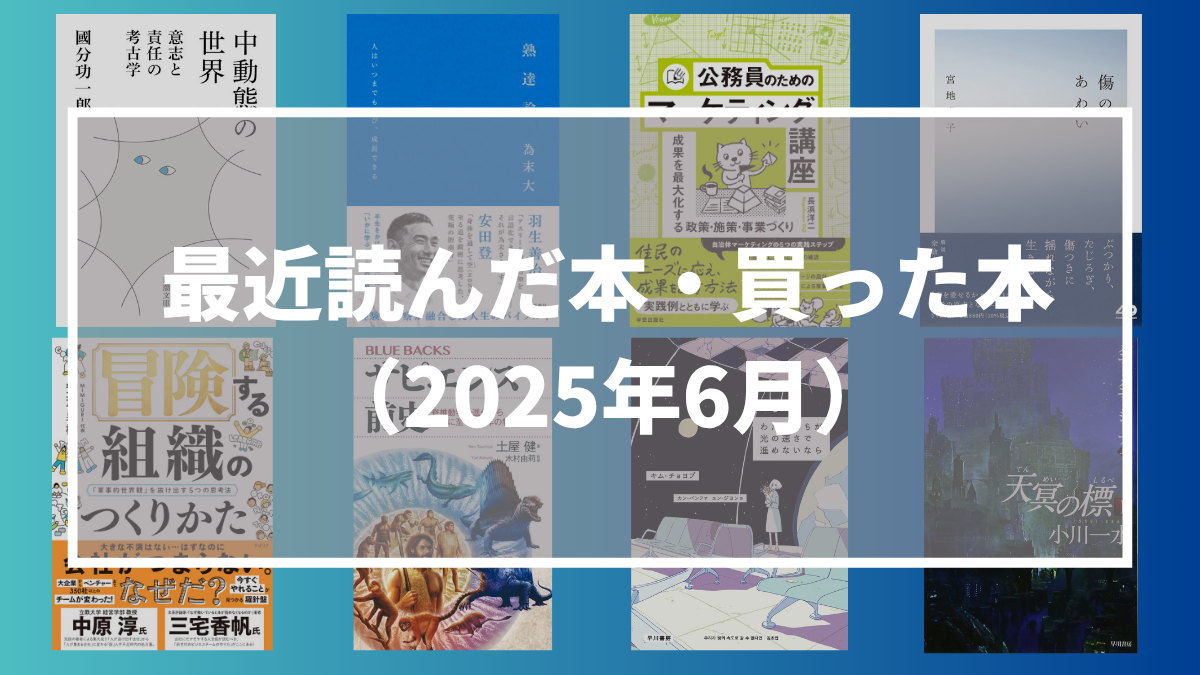 いろいろな本を読んで生きています。紙で読んだ本、電子書籍で読んだ本、オーディオブックで聞いた本と、あと買った本と。単に趣味の本もありますが、仕事に関係していたり考えたい問いがあって読む本もあるのでご紹介します。
いろいろな本を読んで生きています。紙で読んだ本、電子書籍で読んだ本、オーディオブックで聞いた本と、あと買った本と。単に趣味の本もありますが、仕事に関係していたり考えたい問いがあって読む本もあるのでご紹介します。
- 読んだ本
- 『中動態の世界 意志と責任の考古学』(國分功一郎)
- 『熟達論』(為末大)
- 『傷のあわい』(宮地尚子)
- 『公務員のためのマーケティング講座』(長浜洋二)
- 『天冥の標 Ⅰ メニー・メニー・シープ上』(小川一水)
- 『ピーター・ドラッカー 「マネジメントの父」の実像』(井坂康志)
- 『わたしたちが光の速さで進めないなら』(キム・チョヨプ著)(カン・バンファ、ユン・ジヨン訳)
- 『サピエンス前史 脊椎動物の進化から人類に至る5億年の物語』(土屋健著)(木村由莉監修)
- 『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』(國分功一郎)
- 『冒険する組織のつくり方「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(安斎勇樹)
- 『BRUTUS 2025年 7月1日号[星野源と、音楽と。]』
- 買った本・もらった本
読んだ本
紹介は読み終えた順です。
『中動態の世界 意志と責任の考古学』(國分功一郎)
以前単行本で読んだ本を文庫本で再読。やはり最高に面白いです。単行本版を読んでからの数年の間に國分功一郎さんの著作も『暇と退屈の倫理学』『責任の生成』『言語が消滅する前に』『目的への抵抗』などなど読んできていたので本書の議論についても新たな気づきや理解が深まるところが多くありました。文庫版補遺もこの間に國分さん自身が思考を深め進めてきているから社会的な実践に関わるポイントが明快で素晴らしいです。
非営利組織に関わる方、特に対人支援に関わる方にはぜひご一読をオススメします。また、本書の単行本版の出版元である医学書院のシリーズ<ケアをひらく>が好きだという方も、本書を読むと他の書籍への理解が深まったり思考が刺激されたりするので激しくオススメです。
個人的には最近國分さんとは別の角度からアーレントのことを考えていたのでアーレントが「区別」の人であることに色々と思いを馳せながら読みました。
國分さんがアーレントに質問したかったこと、私も私なりの関心から同じことを聞いてみたかったです。
一度でよいので実際に会ってお話をしてみたかった。「ビリーもクラッガードもヴィアも我々そのものではないでしょうか?アレント先生には彼らのようなところはありませんか?」ーーーその際におうかがいしたかったことはただ一つこれである
本書については単行本を読んだ際に書評記事を書いておりますので良ければこちらもお読みください。
『熟達論』(為末大)
先月読んだ為末さんと今井むつみさんとの対談書『ことば、身体、学び』に続けての読了です。
技能を習得、熟達させていくプロセスを「遊」「型」「観」「心」「空」の5つのステップに構造化して解説していきます。為末さんはアスリートということでスポーツを主とした身体技能の例えが多いですがそれ以外の分野の技能であってもある程度応用がきくように感じました。あとがきによると現代の『五輪書』を書きたかったとのことでなるほど、と思いましたが、読みながら思い浮かべていたのは技能習得やその教育のプロセスの際によく引き合いに出される「守破離」との比較でした。「守破離」も良いと思うのですが、プロセスの分解がざっくりしすぎていて熟達者同士の会話ならともかく初学者が自分に当てはめながら試行していくにはおすすめしにくいと感じていました。為末さんのフレームは守破離の解像度を上げてくれたような感覚があって良いですね。自分の関わるテーマ(特に非営利組織の伴走支援者の育成・成長)において遊から空までの5段階がどうなるのか、という点について考えてみたいです。
『傷のあわい』(宮地尚子)
こちらも4月に読んだ『傷を愛せるか』に続けて読みました。アメリカ、ボストンで暮らす日本人たちの傷の物語。『傷を愛せるか』が宮地さん目線のエッセイだったのに対して、本書は臨床やヒアリングの対象を中心に記述するエスノメソドロジー的な著作です。エッセイ的雰囲気もあるので語られる物語は軽くないですが読みやすいです。
精神科医として臨床的に聞く話もあれば友人としての話であったり色々ですが、いずれにしてもインターネット全盛時代以前の話なので現在のアメリカ移住において起こること、経験されることとは少し事情や様子が異なるだろうなと思いながら読み進めました。仕事柄、傷や悲しみを含めて色々な人の色々な物語や境遇には触れてきたつもりでいましたし、小説等も含めていろいろな人生の物語に触れてきたつもりでいたのですが、同じ日本人のことでも全然知らない傷や人生がまだまだあるよなそりゃあ、となんだか当たり前のことを改めて感じる読書でした。
『公務員のためのマーケティング講座』(長浜洋二)
10年前の『NPOのためのマーケティング講座』の続編というか進化版といった内容です。大きな違いは一つにはマーケティング論の中心的な視点としてサービスマーケティングが据えられていることであり、もう一つは戦略や施策を策定する過程あるいは施策を実践する過程を組織の中でどのように進めれば良いかという観点に着目したファシリテーション・コミュニケーションの章が追加されたこと。対象が人(の行動や内面の変化)であることの多い非営利あるいは公益目的の組織、活動においてはサービスマーケティングの視点を持った上でマーケティングに向き合っていくことの重要性は非常に高いと感じるので、公務員だけでなくNPOに関わる皆さんにもぜひ読んでいただきたいです。サービスマーケティングの視点も、ファシリテーション・コミュニケーションの視点もどちらも著者である長浜さんのこの10年の自治体やNPO支援の実践の中で重要なものとして抽出されてきたものが落とし込まれているようで納得感がありました。
前作『NPOのためのマーケティング講座』については別途書評記事も書いておりますので良ければお読みください。
『天冥の標 Ⅰ メニー・メニー・シープ上』(小川一水)
私はだいたい常に4〜5冊を併読しているのですが、併読する本の中に一つは長く潜れるシリーズ物を入れておきたい性分です。今回選んだのが長くあたためていた天冥の標シリーズ。まったく事前情報入れなかったのでメニー・メニー・シープ下巻も、シリーズ全体の今後の話もどう展開していくのか予想が今のところまったくできなくて、それだけ広がりを感じさせる世界観で良かった、というのがシリーズ突入1巻の率直な感想です。楽しんでいきたい。
『ピーター・ドラッカー 「マネジメントの父」の実像』(井坂康志)
非営利組織に関わる中でドラッカーの言葉を紹介する場面はこれまで何度もあったのですが、ドラッカー自身の人生については本書で初めて知りました。ドイツ系ユダヤ人の家庭で生まれ、WW1、ナチス体制下で育ち、イギリスを経てアメリカへ。キルケゴールの実存主義からの影響や日本の水墨画を始めとした美術への関心など知らなかったことが多く、人や組織に対する眼差しや期待がどこから来ているのかが少しわかった気がします。非営利組織関連の書籍でもまだ読んでないものがあるから読みたくなり、買いました。(「買った本」の方でご紹介します)
『わたしたちが光の速さで進めないなら』(キム・チョヨプ著)(カン・バンファ、ユン・ジヨン訳)
韓国の新世代SF作家のデビュー短編集。科学的な知識からの触発や参照はあるし異星人とのコンタクト、宇宙旅行、記憶や人格のデータ化などSFの歴史にもしっかり乗った設定も多いですがあくまでも読みやすいソフトさでSF初心者にも読みやすい作品になっています。
最近注目される韓国文学の流れもしっかり汲んでいてフェミニズムをはじめとして排除されていたもの、弱さとされていたものを照らしつつ人生や家族などの機微を描く短編集ですので、SFファンだけでなく多くの方が楽しめるかと思います。どれも良かったですが、特に思考を刺激されて好みだったのは「共生仮説」「感情の物性」。「感情の物性」は「コト消費」「推し活」など体験や感情が重視される社会の中で考えがいのあるテーマという感じで、あとがきによると同じテーマで長編も書きたいということだったのでいつか読めるのを楽しみにしたいですね。
『サピエンス前史 脊椎動物の進化から人類に至る5億年の物語』(土屋健著)(木村由莉監修)
Audibleを活用するようになって一番良かったのは、BLUE BACKSがたくさん読めること。まったくの専門外だけど興味はある自然科学の分野の入門書として良いのですよね。
本書は生命の進化の中でも、ホモ・サピエンスに連なる系譜を辿り、その系統樹の枝わかれにおいてどのような特徴や性質が現れてきたのかに着目した生命史概説本です。これまでも古生物の進化に関わる本は読んだことがあったのですが、サピエンスへ連なる系統に絞った構成もなかなか面白かったです。特にサピエンスに連なる系統と両生類や爬虫類など他の系統がいつの段階でわかれたのかなど、自分が小中学生の頃習ったものから学説が更新されていて新鮮さを感じるものもちらほらあったのも楽しかったです。
『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』(國分功一郎)
『中動態の世界』を文庫で再読した際にスピノザについてもっと知りたい、というかこれまでちゃんと知る機会がなかったなということでまずは國分先生の新書から。中動態の世界からの関心でいうと、アレントが「線引き、区別」の人だとするとスピノザは「グラデーション、程度」の人なんだな、という印象を受けました。
ただ、まだまだスピノザ哲学の肝心なところはおぼろげにも掴めていない感覚が強い。Audibleのながら聴きの限界という感じもしますが、全体の構成が國分先生っぽくないというか一つの大きな謎を突き詰めていくミステリー小説みたいな雰囲気が薄くて考えが彷徨ってしまうなと主ながら読み(聴き)進めていったのですが、あとがきによると本書は元々は100分de名著のテキストとして書かれたものを元にしているということで、なるほどそういうことか、と納得しました。國分先生は岩波新書でもスピノザ本を出しているのでそちらも読んでみたいと思います。
『冒険する組織のつくり方「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(安斎勇樹)
前作『問いかけの作法』が非常に良かったので楽しみにしていた本作。出会いの衝撃が大きかった前作ほどではないが本作も、自分自身が関わってきた組織の経験や非営利組織へのコンサルティングの中で感じていた課題意識とも通ずる部分が多く面白かったです。
本書では著者が経営するコンサルティングファーム株式会社MIMIGURIが組織開発コンサルティングを行う際のフレームワークが丁寧に解説されています。中心に据えられている視点は副題にも記載のある「軍事的世界観」からの脱却。この視点自体は特段目新しいものではないですが、本書ほど本質的かつ現場の実態に即して述べられているものは私は読んだことがありませんでした。よく「戦略」や「ターゲット」などの用語が軍事由来だとして批判するような言説を見かけますし、言わんとしていることはわかるのですが、そのような表面的な否定だけを行っても「じゃあどうするのか」は一向に見えてきません。一方で本書は、その代案として「冒険的世界観」を提唱するわけですが、単に過去の考え方や知見を否定する訳ではありません。新たな時代や環境に適合する冒険する組織への変革を目指すにしても、これまで培われてきたノウハウやフレームワークの有効性や必要性自体が否定されたり不要になるということではないことをしっかりと据えた上で論が展開していくので納得感がありました。(例えば目標設定のフレームワークとしてのSMART目標に「加えて」ALIVE目標の視点を取り入れる、など)
個人的に組織の戦略策定や組織づくりのタイプを「課題解決型」「価値創造型」に分けて整理、理解することが多かったのですが、本書で語られる内容によってこれまで構造化して整理するのが難しいと感じていた「価値創造型」の組織における考え方が整理されたように感じたのが一番の収穫です。
『BRUTUS 2025年 7月1日号[星野源と、音楽と。]』
雑誌BRUTUSの一冊丸ごと星野源特集号。濃いめのファンとしては買わないわけにはいきません。これまでアルバム『Gen』について様々なところで語られてきたことやラジオで話されていたこと、そして「あちこちオードリー」出演時に語っていた「絶望」「無」「意味からの脱却」など最近の星野源的ニヒリズムについて冒頭のインタビューでより解像度があがった感覚があったのも良かったですが、プライベートスタジオ808の様子やシンセなどの機材解説が個人的には楽しかった。様々な角度から音楽が紹介され、色々聴いてみたいアルバムが増えたのも良かったです。
買った本・もらった本
『なぜ脳はアートがわかるのか』(エリック・R・カンデル著)(高橋洋訳)
以前から関心を持っていて「読みたい本リスト」に長く入れていた本だったのですが、ついに購入しました。直接的には美術鑑賞が趣味の一つであるというところからの関心ではあるのですが、特に私は抽象画や現代美術などパッと見ではよくわからないような美術作品の方こそが好きだったりすのですが、作者が思い描いていたものや伝えたかったものがちゃんとわかっているとは思っていなくて、だとするとこの好きという感覚ってどういうことなんだろう、ということを考えたいなと思っています。また、美術館へ行く習慣やその趣味嗜好はブルデューが指摘する文化資本の一つとしても重要なものとなっているので、だとするとアートが「好き」「わかる」という感覚はどのように育成、伝達されるのかといったことは格差の問題を考えることにも通じると考えていますし、抽象的なものへの理解という感覚について考えることは、非営利組織が描き伝えようとするビジョン等の抽象的な理念や未来像への理解や共感を求めることとはどのように共通し何が違うのか、といったことを考えることにも通じるかも、などなどいろいろな関心というか考えたいことが山積みでとても楽しみにしている本です。
『ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法』(帚木蓬生)
人文書界隈ではさほど珍しくないというかもはや流行り言葉の一つにもなっていると感じるネガティブ・ケイパビリティですが、日本での注目のきっかけを作った帚木さんのネガティブ・ケイパビリティに関する新書、しかも今回は実践編ということでどんな内容なのか気になって購入しました。
『天冥の標 Ⅱ 救世群』『天冥の標 Ⅲ アウレーリア一統』(小川一水)
1巻読み終えて、シリーズを読み進めていこうと思えましたので早速続きを購入しました。
『非営利組織の成果重視マネジメント: NPO・行政・公益法人のための「自己評価手法」』(P・F. ドラッカー、 G.J. スターン)(田中弥生監訳)
読んだ本でご紹介した『ピーター・ドラッカー 「マネジメントの父」の実像』をきっかけに、改めてドラッカーへの関心が出てきました。『非営利組織の経営』は読んでいたけど、こちらは未読だったなと思い、さっそく購入しました。ちょうど組織診断に関する研修を作っているところでもあるので、本書からもヒントを得たいです。
『荒野に果実が実るまで 新卒23歳 アフリカ駐在員の奮闘記』(田畑勇樹)
友人から誕生日プレゼントとして贈っていただきました。読むの楽しみです。
以上です。
「私もこの本読んだ!」というものがあれば感想を聞かせていただけると嬉しいですしオススメの本などもありましたらぜひぜひ教えて下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。










![BRUTUS(ブルータス) 2025年 7月1日号 No.1033 [星野源と、音楽と。] [雑誌] BRUTUS(ブルータス) 2025年 7月1日号 No.1033 [星野源と、音楽と。] [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51M7qK04XIL._SL500_.jpg)





