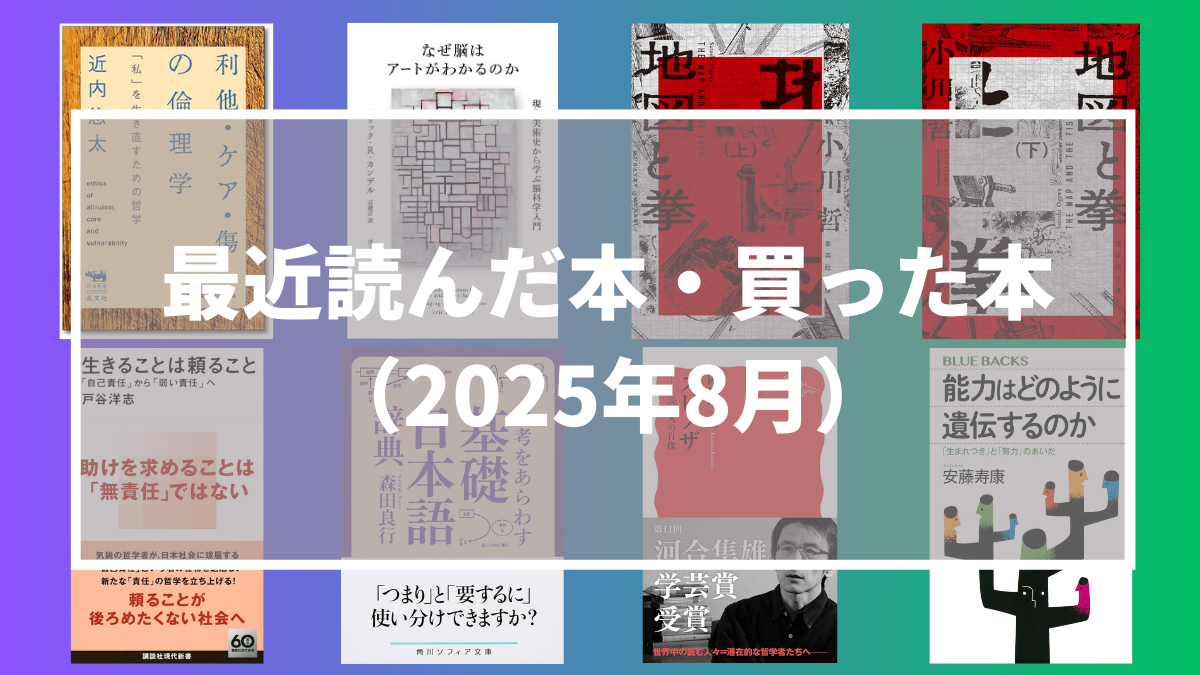
いろいろな本を読んで生きています。紙で読んだ本、電子書籍で読んだ本、オーディオブックで聞いた本と、あと買った本と。単に趣味の本もありますが、仕事に関係していたり考えたい問いがあって読む本もあるのでご紹介します。
読んだ本
紹介は読み終えた順です。
『利他・ケア・傷の倫理学』(近内悠太)
『世界は贈与でできている』の近内さんの二作目。仕事柄寄付などに関わることも多く読まねばなーと思っていたのですが、お仕事で関わるような方々が発売当初からSNSへ感想投稿などしているのを横目になぜか天邪鬼精神が発揮されて手が伸びずずっと未読のままでした。そんな近内さんの2作目ということで気になるけど読むなら1作目からかなぁと散々迷っていたのですが、「利他」「ケア」「傷」と最近の私の関心のど真ん中にいるキーワードがこれだけ並ぶと手を伸ばさざるを得ませんでした。
利他とは、自分の大切にしているものよりも、他者の大切にしているものの方を優先すること。
傷とは、大切にしているものを大切にされなかったときに起こる心の動きおよびその記憶。そして大切にしているものを大切にできなかったときに起こる心の動きおよびその記憶。
ケアとは、他者の大切にしているものを共に大切にする営為全体のこと。
3つのキーワードを他者との関係の中で捉える定義をしながら、それぞれの考察をウィトゲンシュタインの言語ゲームを軸に進めていくというのが全体の流れです。
言語ゲームは続けることそのものに意味があり、他者との関係を断つというのはその他者との言語ゲームから降りてしまうということ、だと。なるほどなぁ。耳が痛い。ウィトゲンシュタインはこれまであまり触れてこなかったので、利他・ケア・傷についてこれまで考えてきたことと重なりつつも異なる角度から考えられたのが良かったです。ウィトゲンシュタインや言語ゲームについてもう少し考えてみたいですね。
『スピノザ 読む人の肖像』(國分功一郎)
続けて哲学に関わる本。こちらはaudibleで読んだものです。
以前國分功一郎さんの『はじめてのスピノザ 自由へのエチカ』を同じくaudibleで聴いて、オーディオブックでスピノザ哲学を受け止めるには限界があるなと感じていたのですが、性懲りもなくこちらもaudibleに出ていたので聴いてしまって、案の定難しかったです笑
スピノザ哲学のポイントを掴めた感じはまだまだしないので、その内紙版で読み直したいなと思いますが、國分先生のガイドでスピノザという人物自体にも触れたことで彼や彼の哲学に対してこれまでと少しイメージが変わる部分があったのは収穫でした。特にスピノザの「神」についての理解や表現について、「神即自然」というスピノザの表現を微妙な時代状況の中での単純なレトリック的表現なのかなと捉えてしまっていた部分があったのですが、宗教的な側面を含めたスピノザの生い立ちや、エチカや他の著作の中で神の存在やあり方がどのように表現されているのかに触れることで、さまざまな角度から考え尽くされていることを感じられるようになったのは良かったです。
スピノザ、いつかまたチャレンジしたいです。
『なぜ脳はアートがわかるのか 現代美術史から学ぶ脳科学入門』(エリック・R・カンデル著)( 高橋洋訳)
ノーベル生理学・医学賞を受賞しているカンデル博士の著作で、脳科学を始めあらゆる領域の研究成果を参照しながらアート、特に抽象画や現代美術の受容について考察する一冊。
私自身がアートの中でも抽象画や現代美術を特に好んでいるということや、母や弟も美術鑑賞が好きなこと(教育や環境、あるいは遺伝の影響のこと)について考えてみたいという関心がまずありました。また、私が主に仕事で関わる非営利組織は理想の地域や社会といったビジョンや社会課題解決などの抽象的な価値を伝え、共感や理解を求めることが重要ですので、人がアートを理解することや好むこととの仕組みを理解することと抽象的な社会的価値への共感や理解にはどのような共通点があるのか、ないのかといったことについて考えてみたく手に取った本です。
視覚から入ってきた情報をボトムアップ的に処理する経路と、入ってきた情報に自身の過去の経験からトップダウン的に解釈する経路の相互作用により各人の文脈による「わかる」が生じる、というのがカンデル博士が説明する基本的な脳科学によるアート理解の仕組みです。
フォルムや色、光など特定の要素のみを意図的に取り出したり、強調したりする抽象画、現代美術には実は脳の情報処理の経路をハックしたようなものも多く、その感じさせる力は理にかなっている部分があることがよくわかり、これらを感覚的に理解し表現したり問いかけるような作品を作ってきたアーティストたちへのリスペクトが増しました。
このアート理解の脳構造的側面に関してのメタ認知が入った状態でアート作品を見にいくとまた違った楽しみ方ができそうで、次に美術鑑賞に行くのがとても楽しみです。
脳の構造としてのアート受容についてはある程度考えられたが元々考えたかったところはもう一歩進んだところにあるので、次はアート作品、特に現代の抽象芸術を好むかどうかに対しての個々人の差がどのように生じるのか、ブルデューの文化資本的な話も含めて考えていきたいと思っています。何読むのがいいかなぁ。
『能力はどのように遺伝するのか』(安藤寿康)
遺伝や進化に関連する新書を立て続けに読んでいた中の一冊。
長年行動遺伝学の研究に携わってきた著者が著者自身の研究データや成果のほか、最新の研究で明らかになっていることが解説されます。
遺伝の影響の大きさを指摘することにはどこか優生学的な気配がついて回るのでタブー視されがちですが、日本の行動遺伝学の第一人者である著者は言います「人間の能力のほとんどは遺伝由来である」ことがわかってきている、と。科学的には何がどこまでわかっていて、そのことは私たち一人ひとりが生きる上で、あるいは私たちが生きる社会のあり方を考える上でどのように活かしうるのかを考えることは重要だと感じます。
特に面白く、一般的なイメージとずれるであろう部分は、遺伝か環境か、という二者択一なのではなく遺伝は環境と相互作用するということや、どのような環境で育つかや環境からの刺激の受け方自体も遺伝に左右されること、そしてそれらを含めて年齢が上がるほど遺伝の影響は大きくなる(一般的なイメージだと生まれたばかりの赤ちゃんの頃が最も遺伝影響が大きく、その後成長する過程においては環境要因の影響が増えていくので年齢が上がるにつれて遺伝の影響は小さくなりそうですよね)、といった話です。
教育やこども、若者支援などを考える上でも視点が広がりそうで、もっと学びたいと感じ、同じく安藤寿康さん著作でより一般向けであろう『教育は遺伝に勝てるか?』を紙版で購入したので読むのが楽しみです。
『地図と拳(上・下)』(小川哲)
第168回直木賞及び第13回山田風太郎賞受賞作。
小川哲さんは前から気になっていたのですが本書が初読みとなりました。
日露戦争前から戦後まで満州を舞台とした歴史改変小説。日露戦争前後から第二次大戦終了後までの満州の地を巡る人々、国々の様々な想いが絡み合った歴史を力強く再構築した物語です。孫悟空という人物が出てきたり「戦争構造学研究所と仮想内閣」という要素があることで歴史改変SF的ではあるのですが、史実のifを描くこと(例えばヒトラー率いるドイツと大日本帝国がWW2に勝っていたら世界はどうなっていたか、を描くディックの『高い城の男』など)が主題ではないので満州を巡る歴史や戦争の流れは基本的に実際の歴史の流れのままに描かれており、それらにまつわる人々の人生や感情には想像力を刺激され深く引き込まれます。
全編に渡る大きなテーマはタイトルにもなっている「地図」と「拳(暴力、戦争)」。戦後80年となる現在も世界では多くの「拳」が振るわれていることはもちろんですが、この物語ならではということでいうと「地図」の現在についても色々と考えながら読むことになりました。日本国内に限れば「拳」と共に並べられる文脈は少なくなっていると思いますが、例えば毎年規模を増す自然災害の復旧により各地で新たな都市や集落が構想され地図が更新されたり、人口減少が進んでいく中でこれまでの地図通りでなくなったり新たな地図を作らねばならなくなったりしているところは多くあるでしょう。新たな地図を作るとき、その周囲にはどのような人や想いがあるのか、歴史的にも地理的にも思考が渦巻きながら想像の広がる素晴らしい小説でした。オススメです。
『思考をあらわす「基礎日本語辞典」』(森田良行)
日本語学者森田良行さんの基礎日本語辞典からあるテーマに関わる単語を抜き出した特別編。昨年読んだ『気持ちをあらわす「基礎日本語辞典」』に続いて同じシリーズから2冊目の読了となりましたが、相変わらず面白いです。
辞書をそのまま読むのも嫌いではないですが、そこまで集中力と好奇心が続くタイプではないので、通常の辞書ではなかなか読む通すことはできません。それがこの「基礎日本語辞典」はきっと辞典そのものを購入しても全編楽しく読み通せるのだろうなと感じる程、スラスラと読み進められます。感覚的には言葉の意味に関するエッセイを読んでいるような感じです。
ひとつひとつの単語の分析、例文、関連語が詳細で、私たちは日常で日本語を話したり書いたりするときに、ひとつの単語でこんなにたくさんの意味の幅を使い分けていたんだなと驚きますし、よくこれだけ分析してわかりやすく解説できるものだと感心します。
今回特に感動したのは助動詞の「〜ない」の解説です。否定、否定疑問、勧誘・命令、否定勧誘、確認(同意を求める形式)、婉曲(念押し)、推量、否定推量、感動・感嘆、否定感動、願望・希望、否定願望と12もの使い分けが豊富な例文と文脈等の解説が11ページに渡ってなされます。これに形容詞の「ない」などはまた別で同じように解説があるのです。すごい。
「基礎日本語辞典」が日本語教育の分野で重宝されたというのもよくわかります。自分が日々使う言葉、読む言葉、聞く言葉にも敏感になれる気がするのも本書を読んで良かったと感じることです。残りのシリーズも読んでいきたいと思います。(文庫化されている残りのシリーズは「時間をあらわす」「違いをあらわす」の2冊)
『生きることは頼ること 「自己責任」から「弱い責任」へ』(戸谷洋志)
書名に興味を引かれ何気なくaudibleで読んだ本だったのですが、素晴らしかった。新書の中では今のところ今年読んだ中でベストです。
副題にもある通り自己責任論について批判的に考える本なのですが、第1章で自己責任という言葉の意味構造や日本社会の中でどのように浸透してきたか解説した後に、著者が提唱する「弱い責任」を理論的に支えることになる3人の哲学者の理論を紹介していくという構成なのですが、まずこの第1章の経緯の解説がとてもわかりやすいです。新自由主義との関連から始まり、イラク日本人人質事件などいくつかの社会的なトピックスをきっかけとして様々な文脈に広がっていったことや、現在では中教審の答申にも自己責任の言葉が使われるようになってしまっていることなど幅広く確認することができます。その後、第3章で自己責任論の背景となっている、自立した個人による意思概念の曖昧さを理解するために國分功一郎の中動態議論を参照します。その上で、弱い責任論を組み立てるために、ハンス・ヨナスの哲学から「誰が責任を取るのか」よりもむしろ「誰に対する責任があるのか」へと責任の捉え方をリフレーミング史、キテイの議論からケアの倫理を参照しつつ社会において私たちがいかに相互に依存し合って社会が成り立っているのかについて検討し、最後にバトラーでまとめて自己責任論に対する「弱い責任」のあり方を論じていきます。
國分先生の中動態の議論などすでに関心を持っていたものも登場しながら、自分が関心を持っていたことや考えたいと思っていたことととても重なりが大きかったので、とてもおもしろかったし、audibleで聴いていても文章が非常にわかりやすいのも良くて、紹介されたヨナス、キテイ、バトラーだけでなく戸谷さんの他の著作も読んでみたくなりました。
買った本
『能力主義をケアでほぐす』(竹端寛)
2021年から開始して今年で5年目となる「コミュニティ読書会(知り合いとやっているコミュニティに関わるテーマについてみんなで学び対話する読書会)」の対象本として購入した本です。9月から10月にかけて読んでいく予定なので、感想は本記事の10月分でお届けできる予定です。
コミュニティ読書会でこれまで読んできた本は以下の記事にまとめています。
『教育は遺伝に勝てるか?』(安藤寿康)
読んだ本で紹介した『能力はどのように遺伝するのか』と同じ安藤寿康さんの著作です。同じく新書ですが、ブルーバックスではないのでより一般向けにはどのような書き方になっているのか気になって購入しました。今読んでいます。
『社会学的想像力』(C・ライト・ミルズ著)(伊奈正人、中村好孝訳)
社会学についてはずっと少しずつ学習を進めているのですが、社会学の古典の中でも教科書的にというか基本的な視点の一つとして一度は学んでおかないとな、とずーっと考えていたのでとりあえずやっと購入する気になった自分をまず褒めたいです。あまり積まずに早めに読みたいところ。
『昭和史(戦前篇・戦後篇)』(半藤一利)
『地図と拳』を読んで満州についてもっと知りたくなり、毎年更新している『戦争と近現代日本について考えられるようになるために私が読んだ本』の記事の候補としても考えていたこちらの本を購入しました。(リンクは新版ですが、私が購入したのは旧版です)
『祈りの海』(グレッグ イーガン著)(山岸真訳)
SFが好きです。好きなのですが、なかなか自信をもってSF好きと言えない自分もいて、それは超有名作家や古典的な作品で未読があまりにも多すぎるからだったりします。ということで、イーガン。以前『ディアスポラ』を読んで圧倒されて、それ以来なかなか手を伸ばせていなかったのですが難解なだけがイーガンではないと聞いているので楽しみです。
『新しい世界を生きるための14のSF』(伴名練編)
同じくSF。日本のSFも大好きです。伴名練編のアンソロジーということで超期待大ですが、なんと800ページ超。なかなか読むのに骨が折れそうです。
『シッダールタ』(ヘルマン・ヘッセ著)(高橋健二訳)
人文書を読んでいる中で繰り返し引用に出会って興味を惹かれる作品がしばしばあるのですが、本作はその中の一冊。ヘッセを読むのは2年ほど前に読んだ『クヌルプ』以来です。楽しみ。
今月のカフェ読書
読書室CAVESTORE

札幌には静かに読書することを推奨するお一人様専用カフェがいくつかあるのですが、その中の一つ。札幌駅近くに来る用事がある際に寄ることが多いです。半地下の店内には、カウンター席の他、一人ずつのデスクのような席が何席かあります。今回の席にはありませんでしたが、店内にも本が置いてあるので手ぶらで行っても読書を楽しむことができます。食事やスイーツも美味しいです。
ロックフォールカフェ

札幌時計台近くのビルに入っているお店。ダークブラウンの調度品で整えられた店内にジャズなどのBGMもセンスが良くとても雰囲気の良いお店です。私はよくカウンター席で本を読みますが、テーブル席も多く、土日は特におしゃべりの声も賑やかめなので、静かに読書というよりはカフェ的な喧騒の中で読みたいという気分のときに良いです。
以上です。
「私もこの本読んだ!」というものがあれば感想を聞かせていただけると嬉しいですしオススメの本などもありましたらぜひぜひ教えて下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。















