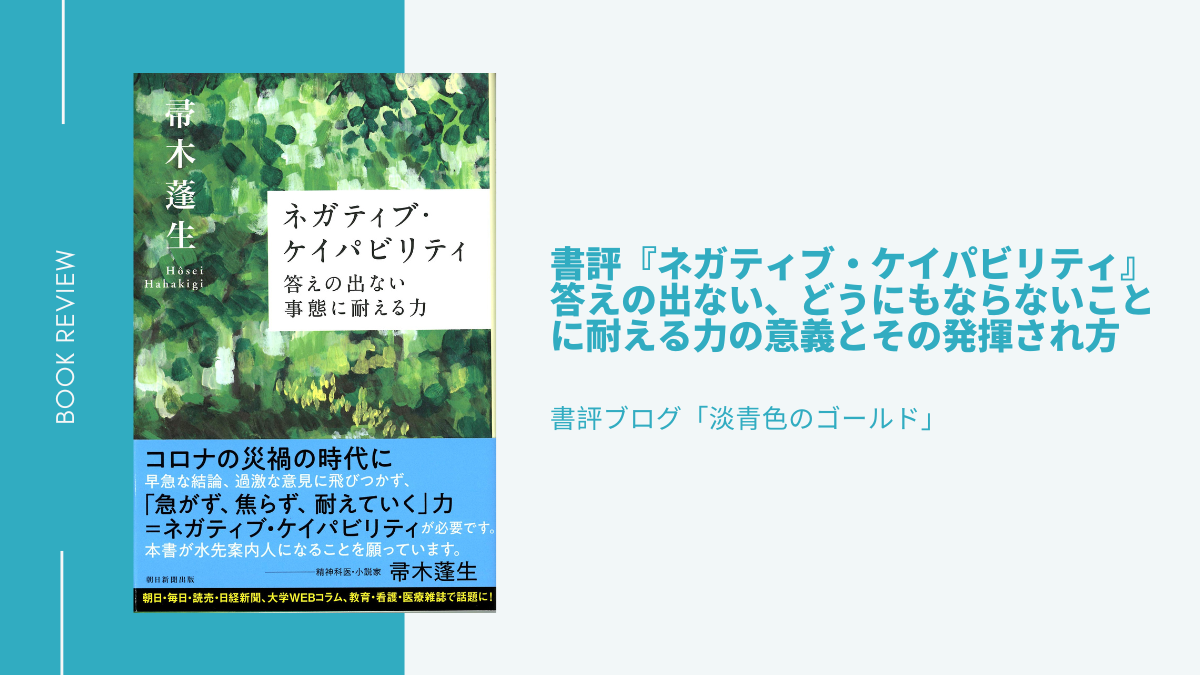
こんにちは。書評ブログ「淡青色のゴールド」へようこそ。本記事は精神科医で作家の帚木蓬生さんの著書『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』の書評記事です。人生や対人関係における視点の持ち方として知っておくといざというときに踏ん張る力を持てるようになるかもしれない考え方で、ぜひ多くの方に知っていただきたいです。
- 内容紹介
- ネガティブ・ケイパビリティとは
- 対人支援職は詩人が世界に接するように相手に接すべきである
- コンサルタントとして大切にしたいネガティブ・ケイパビリティ
- シェイクスピアや源氏物語へのやや過剰な深入りは読者への問いかけか
- 『ネガティブ・ケイパビリティ』を読んだ人にオススメの本
内容紹介
ネガティブ・ケイパビリティとは「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」のことを指します。一般的に現代社会では「なるべく早く明確な答えを出す能力」、つまりポジティブ・ケイパビリティがよしとされており、それができないことは否定的に捉えられます。しかし、人が生きていく上ではどうにも答え出しようのない問題にもしばしば直面しますし、今後の社会はどんどんと見通しの立ちにくいものになっていくと言われる中で、急いで答えを出さずに状況に耐えながら過ごしていく態度を取れる方がむしろ人生に希望を持っていくことができるといいます。ネガティブ・ケイパビリティは、ただ後ろ向きに考えるということではありません。
本書ではネガティブ・ケイパビリティという概念を提唱した詩人のキーツや、その概念の有用性を発見した精神科医のビオンがなぜその概念に注目したのかを辿りながら概念の概要が解説されます。また、医療や教育、芸術などさまざまな分野でどのようにネガティブ・ケイパビリティが活かされているのかについても知ることができます。
先日書評を書いた『ハッピークラシー』で、ポジティブであること幸せであることを目指すべき絶対の理想として置くことの問題点や歪さについて考える中で、関連するテーマとして考えてみたいと感じたのが「ネガティブ・ケイパビリティ」でした。著者が精神科医であることもあって医療現場の事例や話題も多く、私自身が関心を強く持っている対人支援職現場での応用や関連性についても考えることができましたし、似たような関心から学んだり考えたりしているナラティブ・アプローチや社会構成主義、当事者研究、現象学などと合わせて考えるとより深めていけそうな重要な概念だと感じました。ネガティブ・ケイパビリティを扱った書籍はいくつか出ているようですが、ネガティブ・ケイパビリティの定義からして単に明確な定義や答えをわかりやすく書くだけではないアプローチの方が本質的だと感じますし、この概念を提唱したのが詩人キーツで、再発見したのが精神科医ビオンであるということからも作家であり精神科医である著者の解説は全部がわかりやすいわけではないですが、だからこそこの概念を考える上では読む価値のある書籍だと感じます。
Amazonの内容紹介から引用します。
「負の力」が身につけば、人生は生きやすくなる。セラピー犬の「心くん」の分かる仕組みからマニュアルに慣れた脳の限界、現代教育で重視されるポジティブ・ケイパビリティの偏り、希望する脳とプラセボ効果との関係…教育・医療・介護の現場でも注目され、臨床40年の精神科医である著者自身も救われている「負の力」を多角的に分析した、心揺さぶられる地平。
本書の構成
本書は以下のように構成されています。
はじめに ―ネガティブ・ケイパビリティとの出会い
第一章 キーツの「ネガティブ・ケイパビリティ」への旅
第二章 精神科医ビオンの再発見
第三章 分かりたがる脳
第四章 ネガティブ・ケイパビリティと医療
第五章 身の上相談とネガティブ・ケイパビリティ
第六章 希望する脳と伝統治療師
第七章 創造行為とネガティブ・ケイパビリティ
第八章 シェイクスピアと紫式部
第九章 教育とネガティブ・ケイパビリティ
第十章 寛容とネガティブ・ケイパビリティ
おわりに ―再び共感について
本書をオススメする人
本書は以下のような方に特にオススメします。
- 「ネガティブ・ケイパビリティ」の概念に関心のある人
- 医療、教育、福祉、カウンセリング・コーチングなど対人支援的な取り組みに関わる人
- 対話、ワークショップなどの実践に関わりのある人
ネガティブ・ケイパビリティとは
先にも紹介した通りネガティブ・ケイパビリティとは「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」を意味しています。対になるのはポジティブ・ケイパビリティで、これはすぐに明確な答えを出そうとする、あるいは出すことのできる能力のことです。
本書の中でも第九章「教育とネガティブ・ケイパビリティ」で詳しく述べられていますが、現代の教育は予め決まった明確な答えをなるべく早くアウトプットすること、つまりポジティブ・ケイパビリティを養成することを主眼として構成されています。そしてそれは現代社会そのものがポジティブ・ケイパビリティの原理を中心として成り立っているということです。
しかし、私たちが生きていく中では明確な答えが出るようなことばかりではありません。対人関係や社会的な行為の中にはわりきれない、どちらが正しいとは言い切れない問題は数多くありますし、自然災害や偶然の事故、病気など自分自身の力ではどうしようもない事態も少なくありません。また、コロナ禍はその最たるものでしたが、今後の社会はVUCAの時代とも言われ見通しを立てるのが難しくなっていくと言われています。そうした中でポジティブ・ケイパビリティしか持っていないと立ち直れない状況に陥るということも考えられます。
そうしたときに見直されるべき、大切にされるべき考え方として提唱されているのがネガティブ・ケイパビリティです。「ネガティブ」という単語がついているとそれだけで否定的なイメージがあるかもしれませんが、ネガティブ・ケイパビリティは単に消極的、悲観的に考えるということではありません。すぐに答えを出さずにその場の状況や時間が過ぎていくことに耐えていくことによって初めて事態が切り開かれたり好転したりする可能性につながっていくという考え方であり、ネガティブ・ケイパビリティを持つからこそ人生に希望を持つことができる場面があるのです。
ポイントは一人よりも自分以外の他者との関係性の中でこそその能力が発揮されうる余地が切り開かれていくということでしょう。もちろん個人として「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える」ことができ、耐えながら事態が変わるまでなんとか生き延びられる人もいるとは思いますが、本書が提唱するのはそのような強いあり方という訳ではありません。
困難な状況を抱える相手の話を何かすぐに解決策を提示するのではなくまずはじっくりと受け止め聞くことや、聞いてくれる相手がいることの重要性が説かれています。
対人支援職は詩人が世界に接するように相手に接すべきである
本書の著者は精神科医であり、本書の中にも著者自身が実際に日々の診療の中で出会った患者との対話的な事例や、医療に関連するような事例を元にした話題が多く登場します。ただ、これはネガティブ・ケイパビリティを活用することができるのが医療者だけであるという訳ではもちろんありません。医療を始め、看護、福祉、教育、カウンセリング等の対人支援職は広く応用することができると思いますし、コーチングやコンサルタントなどビジネス現場での対人関係、あるいは広くは私たちの日常の人間関係について幅広く応用していくことができるでしょう。
ではそのような対人関係においてネガティブ・ケイパビリティを発揮するためにはどのように相手に接すれば良いのでしょうか。この点についての気づきが、ネガティブ・ケイパビリティの提唱者である詩人キーツの言葉の中から紹介されていたのが非常に面白かったです。
キーツは、作家や詩人は外界に対して自ら働きかけるのではなく、自らの個性を消してただ自然の中に存在する受動的な存在となることで初めて外界のある様を言葉にすることができると捉え、そうした姿勢や能力のことをネガティブ・ケイパビリティとして表現しました。
この考え方を芸術から医学の世界に持ち込んだのが精神科医のビオンで、精神分析医も優れた詩人が世界にネガティブ・ケイパビリティを発揮して接するように、患者との間に起こる現象や言葉に対して、同じような能力が必要であると訴えました。
医療にしろ、福祉、教育にしろ、その分野の中にはそれまでに培ってこられた知見があり、その分野に従事する個人はそうした分野におけるものの見方を専門性として有した状態で対象と接することになりますが、それだけでは十分ではないのではないかという問いかけです。
記憶も理解も欲望もなくと言ったビオンの指摘は、実に大切なところを突いてきます。なまじっかの知識を持ち、ある定理を頭にしまい込んで、物事を見ても、見えるのはその範囲内のことのみで、それ以外に広がりません。
患者が発する言葉、ちょっとした振舞いにしても、精神分析学の記憶や理解があると、それは理論的にはこれこれにあてはまると簡単に片付け、ありきたりの陳腐な解釈になってしまいます。
ビオンは、解釈とはそういうものではない、もう少し開放的で新鮮味に富み、新しい境地に踏み出すような力を有するべきたと説いたのです。
これは医療に限らず非常に示唆に富む指摘だと感じます。理論やフレームワークなどの定式化された知というのはさまざまな事例に共通する要素を抽象化して作られていることが少なくありません(そうではない理論化の仕方ももちろんありますが)。しかし裏を返せばこの抽象化されているということは、個別具体的な事情や状況は捨象されるということです。ネガティブ・ケイパビリティを発揮するというのは、この普段捨象されがちな事情や感情を切り捨てることなく向き合おうという態度ですし、そのように受け止める、聞いてもらえるという経験自体が相手の感情を解きほぐし、展望につながっていく可能性があるというのは、医療や教育などの対人的な仕事の現場においても、家庭や友人関係を含めた私たちの日常生活においても大切にしたい姿勢だと感じます。
本書ではこうしたことをさまざまな角度から教えてくれます。個人的に気づきのあったものをいくつか引用しておきましょう。
答えは質問の不幸である/答えは好奇心を殺す
もうひとつ精神科医が戸惑う理由があります。それは正常な精神状態というのが、非常に多種多様、十人十色だからです。いわば、百人いれば百とおりの正常状態があります。病的なものは、幅が決まっていて、百人の患者がいても、十とおりくらいに種類分けができます。もちろんこのとき各人の細かい個人的な差は捨象されています。枝葉を切り取った上で、分類するからです。ところが正常な精神状態は、枝葉を切り取ると、何にも残らなくなってしまいます。個人差をそのまま尊重して正常な精神状態に対処するのは、とっかかりがなく、手が出しにくいものです。マニュアルがつくれません。
人の病の最良の薬は人である
特に「人の病の最良の薬は人である」というセネガルの言い伝えは薬ではなく、人やコミュニティとのつながりを処方することで、抑うつなどの精神的な課題にアプローチし、患者の幸福度が上がるという社会的処方の考え方とも通じるもので、話を聞く聞いてもらうということの効果やその際に必要な態度としてのネガティブ・ケイパビリティの重要性を強く感じます。(「社会的処方」については本記事末尾の関連書籍紹介の欄でも紹介します)
この辺りの効用について、脳科学的な観点も合わせて解説しているのは本書の良い点です。
人の脳は構造として物事をわかりたがる特性を持っていたり、過去や未来を自分なりに整理して希望的な記憶、展望に作り変えていくような構造を持っていることを脳の構造面の研究にも触れて解説しつつ、脳がそのような構造を持っているからこそ、性急に答えを出したり対処を急ぐのではなく、時間を稼いでいくために話をすること、聞くことが重要(時間が経つうちに自然と脳は希望的な解釈を作り出していく)であり、その意味で科学以前の社会に多く存在し一部は今でも残っている祈祷師や占い師、伝統治療師などの態度にはネガティブ・ケイパビリティが発揮されてきたのではないかという解説も納得のいくものでした。
コンサルタントとして大切にしたいネガティブ・ケイパビリティ
本書を読んだのは先日読んだ『ハッピークラシー』に続く関心で、社会の中でのポジティブさの価値観の強さをどのように考えれば良いかという点について深めたいというのが動機で、もちろんそうした点についても上記の通りいろいろな気付きや学びを得ることができたのですが、自分自身の仕事や日常の人間関係に対しての気づきも多く得ました。
特に、コンサルタントとしてクライアントである個人や組織に関わる際の態度としてネガティブ・ケイパビリティは非常に重要であると感じました。この点についてはまったく新たな気づきを得たというよりも、これまでも大切だと思っていながらうまく整理して言語化できていなかったものに輪郭を与えてもらったという感覚です。
私のクライアントはほとんどがNPO法人等の非営利組織です。課題の状況や関わり方にもよりますが、基本的にコンサルタントというのはフレームワーク等の考え方、物の見方で組織や事業の課題を分析したり整理することで、解決策や改善策をつくっていくことを支援します。私自身が答えを出し提案するということは基本的にしない仕事の仕方、受け方をしていますが、フレームワーク的な思考自体はネガティブ・ケイパビリティとは逆の態度です。
ただ、そうしたフレームワーク的な思考や答えを明確に提示するポジティブ・ケイパビリティ的な態度がまったく不要というわけでもなく、むしろそれらが必要とされている場面も非常に多くあるとも感じます。多くのNPOは何らかの地域課題や社会課題の対処に取り組んでいることが多いのですが、そうした事業・活動はそもそも資本主義的な営利組織の論理では答えを出せずに問題化してしまっている事態に対処していこうという発想の中から出てきていることも多く、組織や活動にも寄りますがNPOは基本的な源流として「わりきれない」「答えは出せない」というネガティブ・ケイパビリティ的なものから生まれているところもあり、組織文化としてネガティブ・ケイパビリティと親和性が高いことも少なくありません。
一方で、そうした発想が答えを出せる問題に対しての視野を狭めてしまっている場面も少なくないと感じており、私のような外部専門家がフレームワーク的な発想で支援できるのは、答えが出せる問題と出せない問題を切り分けるという部分にあるのだろうなと感じます。こうした仕事自体に価値を感じてもらえるかどうかという点をしっかりとクライアントと共有しながら仕事を勧めていくことが重要だなと感じます。
みなさんはご自身の仕事の中で、あるいは日常生活の中でどのようにネガティブ・ケイパビリティを活用していくことができそうでしょうか。ぜひ本書を読んで考えてみてください。
シェイクスピアや源氏物語へのやや過剰な深入りは読者への問いかけか
さて、最後に一点。本書を読む中で少し読み解きや解釈の難しい箇所がありました。第八章の「シェイクスピアと紫式部」です。この章ではネガティブ・ケイパビリティを発揮していた作家としてシェイクスピアと紫式部が提示され、その作品の中にもネガティブ・ケイパビリティ的な態度が表れてることが解説されます。
元々ネガティブ・ケイパビリティを提唱した詩人のキーツがシェイクスピアの作家としての態度の中にネガティブ・ケイパビリティを見出していたということもあり、そもそも芸術分野から登場した概念ですのでそれを発揮した作家について触れるのはそこまで不思議なことではありません。ただ、特に紫式部についてはかなり深入りをしています。紫式部の人生の紹介に続き、彼女が著した『源氏物語』について、ほぼ前編にわたるあらすじの解説が行われ、さらには異国の作家ユルスナールが書いた続編のあらすじまで解説され、約30ページ程こうした記述が続きます。
著者自身がシェイクスピアや紫式部にネガティブ・ケイパビリティの発揮を見出した、という記述はあるのですが、具体的にどのような箇所なのか、作中の登場人物のどのような姿勢がネガティブ・ケイパビリティの発揮だと感じているのか、それほど明晰に書かれているわけではなく、やや蛇足にも感じました。
ただ、「わかりにくい」とか「不要ではないか」と早急に切り捨ててしまう態度をこそ戒めるのがネガティブ・ケイパビリティだったことを思い返すと、著者はあえて少しわかりにくいやりかたでネガティブ・ケイパビリティの重要性を問いかける役割としてこの章を書いたのかなと感じたりもします。
本書を読んだ方にはどのように感じたのか、ぜひお聞きしてみたいところです。
『ネガティブ・ケイパビリティ』を読んだ人にオススメの本
最後に本書を読んだ方や興味を持った方にオススメの本をご紹介します。
『ハッピークラシー』(エドガー・カバナス、エヴァ・イルーズ)
本文中でも触れましたが、私が『ネガティブ・ケイパビリティ』を手にしたのはこの『ハッピークラシー』を読んだことがきっかけでした。「ハッピークラシー」とは「幸せHappy」による「支配-cracy」を意味する造語です。カウンセリングやコーチング、あるいは自己啓発などを活用することで誰もが捉え方次第、発想次第で幸せになれるしなるべきである(ならないのは自己責任である)という考え方が社会に蔓延していることは、幸せの方法論を普及させることによりむしろ多くの人を決して満たされない幸せ渇望に追いやっているのではないかと問いかけます。カウンセリングやコーチングなどの対話的な職業のあり方についても問われていますので『ネガティブ・ケイパビリティ』と合わせて読むと、こうした取り組みの価値と課題を深く考えられるかと思います。
書評も書いておりますのでよければお読みください。
『社会的処方』(西智弘編著)
続いても本文中で触れた『社会的処方』です。ネガティブ・ケイパビリティは個人が一人でなんとか身につけるというよりも、人の話を聞く中での態度として発揮することがより近道であると感じました。そしてそうしたことを実践として社会の中で深めていこうとしているのが社会的処方の取り組みです。実際に制度化されているイギリスの事例の他、日本のさまざまな事例についても知ることができます。
書評も書いておりますのでよければお読みください。
『聞く技術 聞いてもらう技術』(東畑開人)
3冊目は臨床心理士の東畑開人さんの『聞く技術 聞いてもらう技術』です。相手の話を聞くこと、聞いてもらうことの中で発揮される余地があるネガティブ・ケイパビリティという考え方を知る中で、非常に似たアプローチだと感じたのが東畑さんの考え方でした。一般に重要だとされる対話的な営みにおいては「聞く」よりも「聴く」が重要であると説かれることが多いですが、東畑さんはこれを逆転させます。重要なのはむしろ「聞く」であり、日常的には何気なくできているはずの「聞く」ができなくなったとき、つまり「聞けなくなった」「聞いてもらえなくなった」ときの対処を考えていくことが大切なのではないかということを細かなテクニックから本質的な話まで幅広くわかりやすく解説してくれます。
最後までお読みいただきありがとうございました。



